「安定」というレールを降りて、人生の操縦権を取り戻す。かつて夢を諦めた男が挑む、人生の伏線回収

愛媛県松山市生まれ。広島県内の大学を卒業後、新卒で国内大手通信キャリア企業に入社。高知、岡山、大阪、東京などで商品企画やDX推進業務に従事した後、2021年1月にサイボウズ株式会社へ転職。同年、故郷である松山へUターン移住を果たす。来期よりBリーグ「愛媛オレンジバイキングス」の運営会社へ出向予定。
愛媛県松山市。
瀬戸内の穏やかな凪とは対照的に、そのアリーナは熱狂の渦中にあった。
バスケットボールBリーグ「愛媛オレンジバイキングス」の試合会場。
シューズがコートを激しく擦るスキール音、ブザーの轟音、そしてオレンジ色のユニフォームに身を包んだブースター(ファン)たちの歓声。
その熱気の中心で、テラダさんは静かに、しかし確かな高揚感とともに立ち尽くしていた。
彼は現在、サイボウズの社員でありながら、来シーズンからこのプロスポーツチームの運営に携わることが決まっている。
「これを成し遂げたら、もう社会人を上がってもいい」
そう言い切る彼の横顔に、かつて巨大企業の歯車として「死んだふり」をして生きていた影はない。
これは、一度は自分の夢を裏切り、“安定”を選んだ男が、39歳にして「人生の操縦権」をその手に取り戻すまでの再生の記録だ。
広島カープの内定と、ドミニカ行きの切符
それは、およそ20年前に遡る。
大学時代を過ごした広島の街は、いつも赤く染まっていた。
広島といえば、カープ。勝っても負けても、街の人々はカープを語る。赤色は街の景観の一部であり、人々の日常に根付いたインフラだった。
「自分も、街の誇りとなるスポーツビジネスに関わりたい」
その想いは、単なる学生の夢物語ではなかった。強い意志を行動に移し、なんと広島東洋カープの内定を手にしたのだ。
だが、提示された条件は「ドミニカの野球学校への赴任」。
未知の国、未知の業務。そして何より、当時のスポーツ業界につきものだった「激務」への恐怖。その切符の重みに、若き日のテラダさんは怖気づいた。
悩んだ末、選んだのは、日本を代表する大手通信インフラ企業。
そこには「安定」と「社会的信用」、そして優秀な仲間との出会いが約束されていた。
大企業での出世レースで戦う
入社してすぐ高知への赴任が決まり、その後も数年おきに岡山、大阪、東京へと拠点を移す生活が始まった。商品企画やDX推進など、自分の適性に合った業務を任され、成果を出すことにやりがいも感じていた。
「社会人とは、そういうものだ」
テラダさんは、その環境を自然に受け入れた。

周りを見渡せば、自分よりはるかに優秀な先輩や同期がいる。彼らと切磋琢磨できる環境は刺激的で、自分を育ててくれる上司や人事にも感謝していた。
不満なんて、あるはずがない。そう思っていた。
けれど、ふとした瞬間に小さな問いが頭をもたげる。
「あれ。これって自分の人生だっけ?」
辞令一枚で、住む場所が決まる。ライフスタイルが変わる。
会社が敷いてくれたレールは立派で、景色もいい。その上を走ることに疑問を持たないようにしていたが、心の奥底では気づいていた。
自分は、この巨大な船の「乗客」に過ぎない。操縦席には知らない誰かが座り、自分はただ運ばれているだけだ。
優秀な同期たちが「次はどのポストを狙うか」と熱く語り合う横で、テラダさんは少しだけ遠くを見ていた。
大きな組織に身を委ねる安楽さと、自分で何も決められない微かな違和感。
その狭間で、彼は静かに「人生の操縦権」を見失っていった。
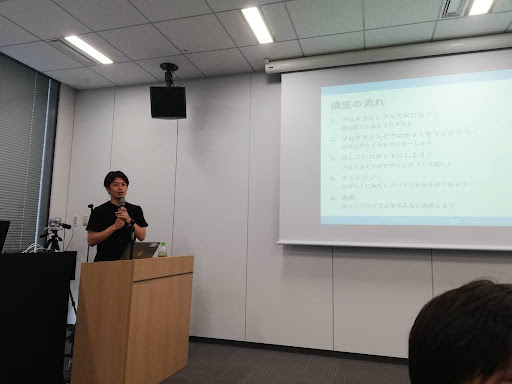
35歳のデッドライン
転機は、世界が静まり返った2020年に訪れた。
新型コロナウイルスのパンデミック。
当たり前だった出社がなくなり、自宅という静寂の中で、思考だけが鮮明になった。
「この先、誰と、どうやって暮らすのが幸せなのか」
妻のお腹には新しい命が宿っていた。自分も、翌年には35歳になる。
ふと、まだ見ぬ我が子の姿を想像して、ある直感が降りてきた。
「生まれてくる子の顔を見てしまったら、自分はもう動けなくなる」
その愛おしい顔を前にしたら、自分は間違いなく「守り」に入る。
今の安定を手放してまで、新しい環境へ飛び込む勇気なんて持てなくなるだろう。
理屈ではなく、感情が自分を今の場所に釘付けにする。その未来が、ありありと想像できた。
「動くなら、今しかない」
まだ見ぬ我が子への情に縛られる前の、今この瞬間。それが、自分の人生を取り戻すラストチャンスだと悟った。
バラバラだったピースが繋がった日
そういえばテラダさんは、イベント会場であるプロダクトに出会い、衝撃を受けた過去があった。
「kintone」。
その革新的なツールを触り、直感した。
「これなら、顧客の成功に本気で関われる。CS(カスタマーサクセス)として勝負してみたい」
純粋なビジネスマンとしての欲求が、彼の中に種として蒔かれた。
そこに、導かれるように見たテレビ番組での言葉が重なった。
サイボウズ社長・青野慶久氏は語っていた。
「商売人が子育てに向き合わなくてどうする」
その瞬間、全てのピースが繋がった。
自分が勝負したいと思える最強のプロダクト。そして、自分の人生や家族を大切にすることを肯定してくれるカルチャー。
ここしかない、と思った。
彼は転職エージェントを使わず、サイボウズ一社に絞って応募した。
落ちたら、今の人生を受け入れて覚悟を決めて生きていく。
それは、退路を断った「賭け」だった。
「あなたの野心は、なんですか?」
そして、2021年1月、サイボウズに入社。半年後には故郷・松山へUターン移住を果たした。懐かしい街の匂い。両親や祖父の笑顔が「帰ってきてよかった」と思わせた。
仕事はカスタマーサクセス。大企業での出世レースという「相対評価」から降り、顧客の成功という「絶対評価」に向き合う日々。
まるで、魔法が解けたようだった。
だが、物語は「幸せなUターン移住」では終わらない。
入社して4年が経過した今年、青野社長が主催する社内大学に参加した際、強烈な問いを突きつけられた。
「あなたの『野心』は、なんですか?」
すぐに答えられなかった。苦しかった。
心の底から満足して働いているはずなのに、その問いかけによって、さらに奥底にある「種火」の存在に気づかされてしまったからだ。
悩む彼に、あるエピソードが語られた。
ビーズソファで有名な「Yogibo(ヨギボー)」の創業秘話だ。あれは、妊娠中の妻がうつ伏せで寝られずに苦しんでいるのを見て、夫が「妻を楽にさせてあげたい」という一心でつくったものだという。
「野心は最初から壮大なものでなくていい。その理想を叶えたいと自分自身が本気で思えるのかが一番大事」
その言葉を聞いた時、およそ20年前に喉の奥に刺さったトゲが、ポロリと落ちた気がした。
脳裏に蘇ったのは、大学時代に見た広島の赤いスタジアム。街中がカープの話題で持ちきりになる、あの愛すべき日常だ。
「自分の野心は、この松山にも、あんな『市民の誇りの象徴』を根付かせることなんじゃないか?」
「週末になれば家族でアリーナへ行く。そんなささやかな習慣が積み重なり、いつしか子どもたちの『幸福な原風景』になっていく未来にしたいんじゃないか?」
それが、彼の本当の野心だった。
「赤」から「オレンジ」への伏線回収
運命とは、時にできすぎた脚本のように動く。
サイボウズが、松山を拠点とするBリーグチーム「愛媛オレンジバイキングス」の経営に参画することが決まったのは、今年6月のこと。
チームワークあふれる社会をつくるIT企業が、チームワークあふれる街をつくるために、スポーツチームを再建する。
そのリリースを見た瞬間、テラダさんの全身に鳥肌が立った。
「これだ」
チャンスはすぐに訪れた。全国のマネージャーが一堂に会する懇親会の夜。
青野社長、そしてこのプロジェクトの鍵を握る人事本部長が揃うその場で、彼は直談判した。
「これ、僕にやらせてください」
その熱意は、真っ直ぐに届いた。
かつて「赤(カープ)」を選べなかった自分が、今、故郷で「オレンジ」のユニフォームを手にする。
これは、ただの憧れではない。大人のリベンジだ。

かつて恐れた「やりがい搾取」や「激務」というスポーツ業界の常識を、サイボウズで培ったノウハウと武器で覆す。
自分のため、家族のため、そしてこれからこの業界を目指す未来の若者たちのために。
これまでのキャリアのすべてを注ぎ込み、スポーツ業界の働く環境を「持続可能な熱狂」へと変えていく。
「もう、野心に蓋はしない」
この場所で絶対にやり切る。
前職で培った業務遂行能力、サイボウズで学んだ自律的な働き方、そして一度夢を諦めたからこそ持てる「強さ」。そのすべてが、この瞬間のためにあったかのように繋がった。
人生の伏線回収が、ここで完了しようとしている。
操縦権を取り戻した大人の選択
地方移住はときに、「都落ち」のように語られることがある。しかし、テラダさんの場合は全く違う。
都市部の不毛な「座席争い」から降り、自分が主役になれるフィールドへ戦略的に移動したのだ。
そこには、代わりの効く「乗客」としての自分ではなく、故郷の熱狂をつくる“代替不可能なドライバー”としての自分がいる。
松山の街角。
かつては「何もない」と思っていたこの街が、今は無限の可能性を秘めたフロンティアに見える。
人生の操縦権を取り戻した大人は、強い。
彼は今、オレンジ色に染まる未来へ向かって、自らの手で力強くハンドルを切っている。
JOIN- 参加する -
「ベターを選べる」情報をGET
自分らしい暮らしや働き方を模索する、
大人のためのコミュニティ。
非公開の求人情報や、
イベントの案内をお届けします。
