「頑張らない私」には価値がないと思っていた。元バリキャリが故郷で見つけた“代替不可能な”生き方

愛媛県松山市生まれ。国立大学在学中にアメリカ留学を経験し、卒業後は新卒で国内大手電機メーカーへ入社。エンジニア職を経て、外資系シェアオフィス企業の日本進出プロジェクト等に従事する。2021年に帰郷し、現在は松山市内の鮨店にて女将を務める。ITや外資系企業で培ったマネジメントスキルを活かし、店舗運営やインバウンド戦略を牽引している。
愛媛県松山市の繁華街、その喧騒を一本外れた路地裏に、静かに灯る行灯がある。
一歩足を踏み入れれば、そこは樹齢数百年の檜(ひのき)が香る、洗練を極めた「聖域」のような空間。
地元の常連客はもちろん、この夜のために海を渡ってきた舌の肥えた食通たちで、白木のカウンターは埋め尽くされている。
その中心で優雅に振る舞う女将の姿があった。
フミノさん、35歳。
大将の呼吸を読み、絶妙な間合いで場を回すその姿は、まさに「天職」。誰もがそう思うだろう。

だが、彼女はかつて“地元の飲食店”で働くというような選択を、最も遠ざけていた人間だった。
これは、資本主義の最前線で「正解」を追い求め、そして一度その道から外れた女性が、故郷で「ベターな選択」をつかみ取るまでの再生の記録である。
「持たざる者」という劣等感
愛媛県松山市で高校時代までを過ごした彼女の半生は、わかりやすいほど「上昇志向」の塊だ。だが、その動機はキラキラした夢ではない。もっと切実で、生々しいものだった。
「現状を変えたい」
ただ、それだけだった。
家庭が裕福ではなかった彼女にとって、勉強は「豊かさ」への唯一の切符だった。
幸か不幸か、幼い頃から勉強ができた。努力しなくても成績は常にトップクラス。高校、大学と複数の奨学金を得る権利を手にした。
だが、一度「もらう側」になれば、その座から滑り落ちることは許されない。
「奨学金を得るために頑張ろう」という健全な動機は、いつしか自分を縛り付ける呪いに変わっていった。
「頑張らないと、私には価値がない」
真面目な彼女にとって、努力は生存戦略そのものだった。
そんな彼女が唯一、心から呼吸ができた時期があった。大学時代に1年間過ごしたアメリカ留学の日々だ。
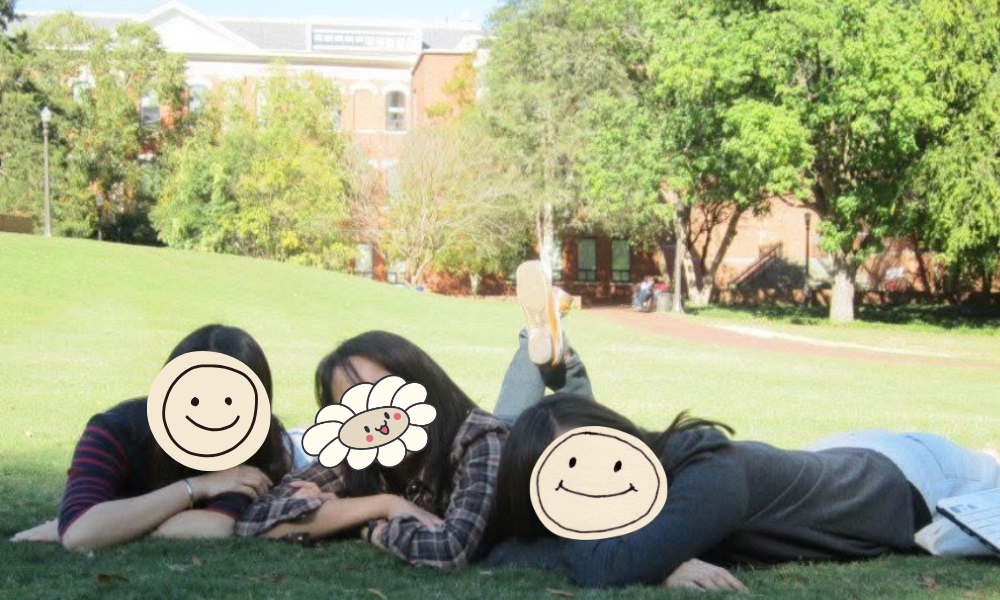
そこには偏差値も、お金のプレッシャーもない。「比較」の軸から外れ、ただの自分でいられた。
「あの1年は、私の人生のハイライトでした」
帰国すると、また他者との比較の中に放り込まれた。
あの自由を取り戻すには、自力で稼ぐしかない。
自分の「強み」や「好き」に向き合うよりも、誰からも後ろ指をさされない「正解」の人生を歩むことこそが、正義だと思った。
本当は、子どもの頃から「レジのチェッカー」のような、現場のオペレーションを回す仕事にときめきを感じていた。
けれど、そんな本音には蓋をした。「稼げない仕事は選べない」。
目指したのは、高収入で、グローバルで、誰もが羨むホワイトワーカー。
彼女は自分の感情を殺して、東京行きの切符を掴んだ。
東京での生活と電池が切れた瞬間
新卒で選んだのは、日本を代表する大手電機メーカー。
大学時代に学んだ情報系の知識が生かせる環境。SEとして、早く一人前になろうと意気込んだが、入社してすぐ違和感を覚えた。
多くの会社員が当たり前のようにこなしている、「組織のルールで働く生活」がしんどかった。
先輩に相談しても「いつか慣れるよ」と言われるだけで、どうにも解決できなかった。
2年ちょっとで限界が訪れた。
「仕事選びを間違ったのかも」
もっと自分に合った仕事をしようと思った。都心に本社のある企業で、総務の職に転じたが、そこでも結局やりがいを感じられず、3年程度で職を変えようと考えた。
キャリア迷子になりかけていた彼女が次に選んだのは、当時“黒船”として上陸したばかりの外資系シェアオフィス企業だった。
そこは、まさに戦場だった。
朝6時に家を出て、夜22時まで働く。新しい働き方を日本に創るという使命感。
顧客の反応がダイレクトに返ってくる環境は刺激的で、アドレナリンが放出され、疲労を感じなかった。さらにアメリカの企業文化でもある「up or out(上に上がるか退職すか)」というハイプレッシャーな環境で、休む暇はなかった。

だが、人間の体は正直だ。無理な「頑張り」は続かない。
ある朝、プツンと音がした。電池切れだった。
立ちあがろうとしても、体が動かない。思考がまとまらない。
初めてやりがいを感じた仕事なのに、頑張りたいのに、できない。
東京のひとり暮らしのアパートで、定職につかず、ただ眠る日々を過ごした。
お金の不安が強烈に襲ってくる。なんとかここから脱したい。でも、うまくいかない。
見かねた兄が、迎えに来た。
「一旦、愛媛に帰ろう」「いやだ、帰りたくない!」
攻防の末、結局東京の部屋を残す、という条件で故郷へ連れ戻された。
31歳だった。
何もないと思っていた場所にすべてがあった
実家の布団の中で、天井を見つめ続けていた。
支配していたのは敗北感だった。
目指していた高い目標に、一度は到達したものの、自分には向いていないことがわかった絶望。
「私はもう、終わった人間なのかも」
引きこもる彼女を外へ連れ出したのは、地元の同級生たちだった。
彼らは、東京での肩書きも、年収も、挫折も気にしない。
ただの「フミノ」として関わってくれた。
その中に、現在の夫となる男性がいた。同級生のひとりだった彼は、鮨職人になっていた。
なりたいものがわからずフラフラしていた自分とは違い、やりたいこと一本で生きていた。
純粋に、その姿がかっこいいと思った。尊敬した。
結婚し、彼と共に店に立つようになり、高級寿司店の「女将」という仕事を始めて、彼女の中で眠っていた才能が爆発する。
彼女の働き方は、いわゆる伝統的な女将のそれとは一線を画していた。
ただ笑顔で酒を注ぎ、空気を読むだけではない。頭の中は、エンジニア時代のように常にロジカルに回転している。
顧客データを緻密に管理し、好みを分析する。インバウンドの動向をリサーチし、集客戦略を練る。そして、その日のオペレーションに課題があれば、即座にPDCAを回して改善する。
かつて東京のオフィスで培った「システム的な思考」と「プロジェクトマネジメント」、そして外資系シェアオフィスで身につけた「コミュニケーションマネジメント」のスキルが、ここでは最強の武器になった。
一見、アナログの極みに見える鮨屋のカウンターの中で、彼女は高度な「戦略を考えて実行」していたのだ。
「地元には何もないと思ってたけど、離れてみたら、豊かな資源に気がついた」
瀬戸内の豊かな魚、美しい水、四季折々の食材。
それらを、自分のビジネススキルで「体験」として設計し、世界中の顧客へ届ける。
そして何より、ここには「他者との比較」がない。
かつてアメリカ留学で感じた「ありのままの自分でいられる解放感」が、意外にも故郷・松山にあったのだ。
AI時代に選ぶ「手ざわりのある仕事」
松山市内、やわらかな冬の陽光が満ちる新築の一軒家。
彼女は今、広々としたリビングで2歳になる子どもと笑い合っている。
東京のワンルームで見た悪夢のような日々は、もう遠い過去だ。
フミノさんは確信を持って語る。
「地方で、地産の食材を使って、遠方からいらっしゃるお客様向けに“食”という体験を提供する。これって、AIがどれだけ発達しても代替できない仕事なんですよね」
東京で情報やシステムという「コピー可能なもの」を扱っていた彼女が、故郷に戻り、「絶対にコピーできないもの」を扱う仕事にシフトした。
かつてしがみついていたホワイトワーカーの仕事は、今やAIに脅かされている。
一方で、彼女が今立っている場所は、テクノロジーが進化すればするほど、その希少性が高まる場所だ。
「今日もお店には、東京や海外から、ここでしか体験できない価値を求めてお客様がいらっしゃいます。目の前のお客様を笑顔にできるこの仕事を誇りに思っていますし、とにかく楽しいんです。」
その言葉には、かつてのような「他者との比較」におびえる響きは微塵もない。オンリーワンのキャリアを選び取った、確固たる自信がある。
窓の外には、穏やかな松山の空が広がっている。
フミノさんのように、自分の本質と、地方の資源を掛け合わせる。
それこそが、東京で戦う以上の「オンリーワン」になるための、最も賢い生存戦略なのかもしれない。
JOIN- 参加する -
「ベターを選べる」情報をGET
自分らしい暮らしや働き方を模索する、
大人のためのコミュニティ。
非公開の求人情報や、
イベントの案内をお届けします。
